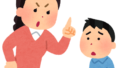3歳頃は、大人と上手に会話できるようになる子が多いですね。
いくら個人差が大きいとは言っても、自分の子が他の子に比べて言葉が遅いと心配になりますよね。
そこで今回は、3歳児が平均的にどれくらい話せるようになるのかや、言葉が遅れているときの対処法などを紹介します。
3歳児の言葉の発達の目安
3歳頃の言葉の発達の目安を、ご紹介します。
三語文以上を話せるようになる
「二語:パン、たべる」という二語文から、「三語:〇〇ちゃん、パン、食べる」 「四語:〇〇ちゃん、丸い、パン、食べる」など、三語文、四語文を話せるようになってきます。
大人やお友だちと簡単な会話ができるようになる
大人だけでなく、同年代や歳上のお友だちとうまく言葉でコミュニケーションをとれるようになります。
いくつかの言葉をカテゴリーにまとめて理解できる
3歳になると、理解力も高くなります。
今までは「パン」「りんご」など単体で覚えていた言葉も、パンとりんごは「食べ物」といったカテゴリーとして考えられるようになり、より新しい言葉を覚えやすくなります。
このカテゴリーは他にも、色、数、身体の部位、動物、などがあげられます。
目に見える”物”だけでなく、目に見えないことの言葉も理解できるようになる
「大きい/小さい」「くさい」「まぶしい」などの目に見えない形容詞やあいさつが理解できるようになります。
以上のように、”言葉が話せる”ようになるのはもちろん、”言葉がもつ意味の理解が深まる”、”言葉同士を結びつけられる”ようになるのが3歳における言葉の発達段階の特徴です。
ただ言葉の発達は、個人差が大きいものです。
意味のある言葉も、1歳前から話す子もいれば、2歳になる頃にやっと話す子もいます。
ですので3歳ごろの子どもは、ペラペラとおしゃべりをする子や、まだ二語文を話す子など、様々な発達段階の子がみられます。
3歳児の言葉が遅れている目安は?発達障害の可能性は?
言葉の発達が個性で遅れているとか、そういうレベルではなく大幅に遅れているという場合は、専門の機関で訓練や指導を受ける必要があります。
では、どういう場合に「明らかに」言葉の発達が遅れているといえるのでしょうか。
ことばの発達のおおまかな目安
「意味のある言葉を一語話す」
9か月で 25% の子どもが、1 歳半ころには 90% の子どもが話し始めます。「二語文を話す」
19 か月(1 歳 7 か月)で 25% の子どもが、2 歳 4 か月で 90% の子
が話し始めます。(デンバー発達判定法より)
明らかなことばの遅れの目安
2 歳までに単語が出ない
3 歳までに二語文を話さない。引用元:愛知県小児科医会
これによると、「3歳の時点で二語文が話せない」という場合は、明らかに言葉が遅れているということになります。
このような場合は、市町村などの自治体や、子育て支援の場、保育園や幼稚園の先生、乳幼児健康診断のときなどに相談をしてみましょう。
言語訓練や指導などをしてくれる専門機関や病院を紹介してもらえます。
こういったところに通うことで、少しずつ改善されることが多いです。
筆者は幼稚園で勤めていた経験がありますが、3歳すぎで入園した子がかろうじて一語を話せる程度でした。
しかし、言語訓練に通い始めてどんどん話せる言葉が増え、卒園する頃には周りの子ほど流暢ではないものの、会話が成立するほどになりました。
言葉の遅れが気になるのであれば、一度相談してみましょう。
発達障害チェックリストまとめ
専門家に相談する前に、発達障害のチェックリストをまとめましたので、テストしてみるのもいいかもしれません。
| ADHD | ADHD NAVI
ADHD.co.jp・・・受診用のチェックリスト |
| 自閉症 | キッズハグ |
※ 発達障害は病名がたくさんあって分かりにくいですが、りたりこ発達ナビ様で図解で紹介されていて分かりやすいです。
言葉が遅れる原因と対処法
「うちの子もしかして言葉が遅れてる?」と感じたら、以下の事に当てはまらないかチェックしてみましょう。
もし思い当たることがあれば、対応してみてくださいね。
テレビやスマートフォンの見せすぎ
忙しいときや静かにしていてほしいとき、テレビの子ども番組やスマートフォンの動画は便利ですよね。
しかし、これらは一方通行のコミュニケーションで、言葉を覚えることはできても子どもが言葉を発することはないですよね。
たまにならいいですが、毎日長時間見せていると言葉を話す機会はなくなってしまいます。
愛知県小児科医会によると、テレビやビデオなどを長時間見る子供は、言葉の発達が遅れがちだそうです。
テレビやスマホを見せるときは、「2話だけ」「病院の待ち時間だけ」など、時間や場合を限定し(長くても1日2時間以内にしましょう)、約束してから見せましょう。
テレビやビデオは自制して(1 日 2 時間以内に)、見る場合は一緒に楽しめるようにしましょう。
テレビやビデオの視聴時間の長い子どもの中に、ことばの発達が遅れていることがあります。引用元:愛知県小児科医会
話さなくてもよい環境である
子どもの気持ちや欲求を、親がすぐに感じ取って何でもしてあげていると、言葉を話さなくても不自由なく過ごせるといった場合もあります。
例えば、子どもが取って欲しいおもちゃを指差せばママがすぐに持ってきてくれるなど、何も言わなくてもやってもらえる環境にいると、言葉を話す機会がなくなってしまいます。
子どもが何をして欲しいか分かっていても、あえて「どうしたの?」「おもちゃが欲しいの?」と分からないふりをしたり聞いてみたりして、子どもから何かを伝えようとする機会を与えてあげましょう。
言葉の理解力が乏しい
そもそも、言葉の意味を理解していないと、言葉は出ません。
「食べる」という意味が分からなければ、「パン たべる」といった二語文は出てこないですよね。
こういった場合の対処法は、とにかくコミュニケーションをとることです。
ママが見本を聞かせるように、「服、着ようね」「うんち、出たね」「電車、バイバイ~」「おてて、洗おうね」など、子どもに分かりやすいように二語や三語くらいの短い文で話しかけましょう。
絵本などを利用するのもいいですね。
この他にも、このような原因が考えられます。
- 個性や性格で、ただ単に成長がゆっくりめ
- 双子や三つ子などの多胎児
- 聴覚に問題がある
- 自閉症などの発達障害
このような場合は、よくコミュニケーションを取りながらゆっくりと成長を見守ってあげましょう。
また、発達障害については、言葉の面だけでは判断できるものではありません。
その他の成長や、人との関わり方の様子、理解力など、様々なことを総合的に見て診断されます。
言葉の発達が遅れている・早いから発達障害だ!と決めつけないようにしましょう。
子どもの言葉を引き出すコツ
子どもが言葉を話すようになるには、身近な人とのコミュニケーションは欠かせません。
言葉の発達を促すために意識的に関わってあげましょう。
簡単な言葉で話す
子どもが理解しやすいように、簡単な言葉でゆっくり、はっきり話しましょう。
子どもの興味関心に寄り添う
子どもが見ているものや興味をもっているものに対して、その時に「電車、速いね」「ワンちゃん可愛いね」というように言葉かけをしましょう。
子どもに選ばせたり簡単なお手伝いをさせてあげる
おもちゃや着る服などを子どもに選ばせることで、色や大きさなどの概念の理解につながります。
また、子どもにお手伝いをさせるときの「ティッシュとってきて」「コップお片付けしようね」などの声かけが、物の名前や言葉の意味を覚えるのにちょうど良いです。
効果音をうまく使う
車が走る「ブーブー」、手を洗うときの「じゃーじゃー」ふりかけをかけるときの「パラパラ」など、同じ音をくりかえす効果音は、子どもにとっては話しやすいことばです。
こういった効果音を活用し、子どもの発語を促しましょう。
さいごに
言葉の発達の遅れには、ただ単に個性として遅れているだけで大きくなってくると目立たなくなる場合と、聴覚や発達の障害がある場合があります。
子どもへの関わり方や環境を見直しても改善しない、明らかに大幅に遅れている、といった場合は相談してみましょう。